八事の杜新聞
季刊で医療やクリニックに関するトピックを掲載しています。
待合室に置いてありますのでご自由にお取りください。
クリック/ダブルクリックで目次が開閉します。
2017年 秋・冬号
「疾病予防のために」
「新内閣に望むこと」
2017年 夏号
「かぜの症状のながれ」
「当院でできる名古屋市の検診」
2017年 春号
「高齢者と運転」
「ワクチン接種について」
「震災6年目、忘れてはいけません」
2016年 冬号
「毎度おなじみ『禁煙のすすめ』です」
「新年に向けて」
2016年 秋号
「B型肝炎のワクチンが定期接種になります」
「今期の各種予防接種について」
2016年 夏号
「4月からの医療政策の変更点」
「校医・校医として感じること」
「最近気になること」
2016年 春号
「大人の発達障がい(神経発達症)」
「胃や腸の検査、X線とカメラ(内視鏡)のどちら?」
「3月11日に想う」
2015年 冬号
「再びスマホ」
「医療保険のお話」
「医療の原点を考えさせてくれる映画」
2015年 秋号
「ワクチンに関するお知らせ」
「小児科の診察室から(待つことと急ぐこと)」
「帯状疱疹(ヘルペス)について」
「東北の被災地に行ってきました」
2015年 夏号
「5月31日は世界禁煙デーでした」
「スマホに子守をさせないで」
「 医療者としての願い」
2015年 春号
「子どもたちの未来のために」
「アレルギーのお話」
「発達障がいについて」
2014年 冬号
「今期の感染症情報」
「過活動膀胱」
「年末でも忘れてはいけないこと」
2014年 秋号
「今期のワクチン接種について」
「ワクチンよもやま話」
「中性脂肪が高いといわれたら」
2014年 夏号
「夏の感染症について」
「待合室をリフォームしました」
「エコスタイル実施中」
「小児科医の想い〜最近の世相」
2014年 春号
「予防接種制度の変更」
「胃がん発生の二重奏」
「4月から医療費が改定されます」
「あの震災から丸3年経ちました」
2013年 冬号
「ウイルス?細菌?どう違う?」
「予防接種の接種回数」
「エコ生活の工夫と楽しみ」
「小学生の男の子の体験談」
2013年 秋号
「ワクチンについて」
「腰が曲がる前に・骨折を起こす前に」
「保育園や幼稚園に通う子どもたちの健康のために(第3版)」
「カフェレスト木馬とNPO法人・ゆうこうの家」
「福島の子ども達のその後」
2013年 夏号
「予防接種関連いろいろ」
「小児科医の想い」
2013年 春号
「ワクチンの定期接種」
「垣間見たアメリカの医療事情」
2012年 冬号
「人は血管と共に老いる」
「改めて禁煙の勧め」
2012年 秋号
「『ガン適齢期』」
2012年 夏号
「予防接種制度の見直しと今後の見通し」
「NPO法人『ゆうこうの家』と 喫茶『木馬』」
2012年 春号
「花粉症のお薬」
「新しいワクチン」
「認知とは?」
2011年 冬号
「予防接種で予防できる病気」
「予防に勝る治療なし(未病)」
「内部被爆と外部被爆」
2011年 秋号
「インフルエンザ予防接種の接種量が変わりました」
「震災後半年。今私たちにできること」
2011年 夏号
「ワクチンで予防できる病気」
「夏です。こんな病気に気をつけましょう」
「チャンピックス(禁煙補助剤)」
2011年 春号
「新ワクチンの認可、中止、そして?」
「心の病気」
2010年 冬号
「任意予防接種の全額助成」
「時間外の救急受診」
「慰安旅行記(台北)」2010年 秋号
「ワクチン行政の流れ」
「ワクチンに関する豆知識」
「名古屋市におけるワクチンの助成」2010年 夏号
「いろいろな夏かぜ」
「8月の思い」2010年 春号
「再々度新しいワクチンについて」
「当院でできる検査」2009年 冬号
「新型インフルエンザ 三たび」
「内科の診察で何がわかるの?」2009年 秋号
「今秋のワクチン情報」
「続・新型インフルエンザ」
「再び子宮頸がんについて」2009年 夏号
「夏のトラブルいろいろ」
「新型インフルエンザ」
「ワクチン情報」2009年 春号
「花粉症対策」
「インドネシア人留学生の投書」
「医療機関で配布される薬剤情報について」2008年 冬号
「ワクチン情報」
「冬の定番ウイルス」
「ベトナムのツーズー病院を訪ねて」2008年 秋号
「インフルエンザワクチン豆知識」
「新しい禁煙薬」「外来小児科学会」2008年 夏号
「溶連菌感染症が流行っています」
「"プラスことば"と"マイナスことば"」2008年 春号
「麻疹・風疹ニ種(MR)混合ワクチン3期・4期」2007年 冬号
「胃腸風邪が流行っています」
「地球のために・子供たちの未来のために」2007年 秋号
「予防接種の勧め」
「外来小児科学会」
「来年度からの新制度について」2007年 夏号
「汗をかこう」
「健康で楽しい老後を…骨粗しょう症を予防しましょう」他2007年 春号
「いまどきの医療事情」2006年 冬号
「風邪かと思ったら・・・」
「再び・禁煙の勧め」2006年 秋号
「外来小児科学会のご報告・感想」2006年 夏号
「オムツはいつとるの?」
「メタボリックシンドローム」2006年 春号
「点滴のお話」「血液検査のお話」2005年 冬号
「インフルエンザについて」
「予防接種のお話」
「胃のピロリ菌感染」2005年 秋号
「病気の予防に取り組みましょう」
「日本外来小児科学会年次集会の報告」2005年 夏号
「食中毒や熱中症、日焼けに注意!」
「新しいワクチン体制」2005年 春号
「風邪?それとも花粉症?」
「夜のトイレが近いのですが」2004年 冬号
「混合診療解禁って何?」
「STD(性感染症)とHIV(エイズ)」2004年 秋号
「我が家の子育てチェックリスト(外来小児科学会のご報告)」2004年 夏号
「夏の健康便り」2004年 春号
「(軽度)発達障害児・者に対する地域医療を目指して」2003年 冬号
「冬に流行する病気と留意点」2003年 秋号
「外来小児科学会のご報告」2003年 夏号
「夏の健康チェックポイント」2003年 春号
「ぐっすり眠れるためには」2002年 冬号
「インフルエンザQ&A 」2002年 秋号
「小児の救急 医者の本音・患者の本音」2002年 春号
「仮面うつ病という言葉を御存じですか」2001年 秋号
「骨粗鬆症について」
「歩き疲れを取る簡単マッサージ」
予防接種・検診のご案内
当院で行っている各種検診、カウンセリング、予防接種、禁煙指導などのご案内です。
→ご予約はこちらからどうぞ
受診されるときは・・・
待ち時間を極力減らし、スムーズに診察を行うために、ご協力をお願いいたします。
NPO法人 ゆうこうの家
当院の療育部門は「NPO法人 発達・心理相談センターゆうこうの家」として 独立しました。
夜間や休日には
名古屋市東部・南部で
夜間・休日に受診できる施設と
電話相談窓口のリストです。
受診の前に・・・
→子供の発熱時の看護
リンク
提携医療機関等のリンクです。
メール
八事の杜新聞 季節便り 2017 夏
かぜはウイルスが原因ということはよく知られています。
冬のかぜの代表はインフルエンザですが、暑さに向かう頃から、ヘルパンギーナや、手足口病、プール熱などのいわゆる夏かぜが流行りだします。
かぜには鼻水や、咳を伴う呼吸器系のかぜと、嘔吐、下痢などを伴う胃腸系のかぜがあります。
かぜと紛らわしい病気が春・秋の花粉症、初夏に流行しやすい溶連菌感染症、
サルモネラや、キャンピロバクターなどの菌に汚染された食べ物で感染する胃腸炎などがあります。
今年5・6月は溶連菌感染症が大流行です。子どもも大人も感染しています。
初めに受診した医院で、のどの炎症と発熱で抗生剤の処方をされた女性が、
鼻炎症状もあったため翌日耳鼻科を受診、抗生剤は止めてくださいと言われて中止したところ、
高熱とのどの炎症が悪化し、また脱水のため当院を受診されました。
溶連菌感染症だったので、抗生剤の十分な投与が必要な患者さんでした。
 かぜの症状のながれ
かぜの症状のながれ
かぜは前触れ症状として、だるい、眠い、食欲不振などがあり、
それに続いて呼吸器系の場合は、熱、のどの痛み, 咳などが出て、
熱が下がり始めるころ、だるさもなくなり、痰を伴う咳になって、痰を出しきると治ります。
従って痰を出すための咳はむやみに止めない方がいいのです。
胃腸系のかぜの場合は、熱、吐き気、嘔吐、下痢と続き、ウイルスがいっぱいで、未消化の食べ物や、粘液の混じった便が出てしまえば、快方に向かいます。
炎症を起こした上皮の回復には約1週間前後を要します。
大人はかぜの前触れ症状を感じることができますが、子どもは前触れなく突然本来の症状が出ることが多いので、親は「急に」かぜをひいたように感じます。
かぜの「治療」は治すことが目的ではありません。症状を軽くして自力での回復の手助けをすることです。ウイルスに抗生剤は効きません。
咳止めや、解熱剤、点滴も症状を軽くすることが目的ですが、
溶連菌に対する抗生剤や、インフルエンザに対するタミフルは治療が目的です。
どちらも自力でも回復することが多いですが、溶連菌は急性腎炎などの合併症の予防、
インフルエンザの場合は、脳炎や肺炎の予防とともに、強い感染力による大流行を防ぐためです。
たかがかぜ、されどかぜ、確実な診断と、無駄のない治療、落ち着いた対処を医療者、患者さんとも心掛けたいものです。
 当院でできる名古屋市の検診
当院でできる名古屋市の検診
| 胃がん検診 | 40歳以上 | 年度に1回 | 胃X線検査 |
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 年度に1回 | 便潜血検査(2日法) |
| 肺癌/結核検診 | 40歳以上 | 年度に1回 | 胸部X線検査 |
| 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 年度に1回 | PSA(血液)検査 |
| 骨粗しょう症 | 45・55・65歳の女性 | 年度に1回 | 骨量検査 |
| 40・50・60・70歳の女性 | 年度に1回 | 骨量検査(無料) |
※自己負担金は各検診500円・年齢によっては自己負担金なし)
※子宮頸がんは20歳以上の女性に、乳がんは40歳以上の女性に2年度に1回、
各検診500円で実施しています。検診可能な医療機関での受診をお勧めします。
若い女性に子宮頸がんが増えてきて、1年間に約3000人の方が亡くなっています。
恥ずかしいという意識は理解できますが、多くの患者さんを診ている医療者にとっては子宮も乳房も身体の一部であり、 いかに素早く正確に、苦痛を与えずに検査するかが大事で、それ以外に気を取られる余裕はありません。
のどや鼻を診てもらう感覚で受診されるのがコツかと思います。がんは早期発見と予防が大事です。
B型肝炎ワクチンとHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンにより、ウイルス感染で発症する肝がんと子宮頸がんはほとんど予防できます。
HPVワクチンは副作用の不安から接種勧奨が中止されて4年たち、感染拡大が予想されます。 筋肉痛やしびれなどの症状は、アンケート調査によると接種していない人にも同じくらい発症しています。
どちらも定期接種です。定期接種年齢内の接種はもちろんのこと、任意接種となる年齢でもぜひ接種されることをお勧めします。



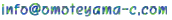
 2017年 春号
2017年 春号