八事の杜新聞
季刊で医療やクリニックに関するトピックを掲載しています。
待合室に置いてありますのでご自由にお取りください。
クリック/ダブルクリックで目次が開閉します。
2017年 秋・冬号
「疾病予防のために」
「新内閣に望むこと」
2017年 夏号
「かぜの症状のながれ」
「当院でできる名古屋市の検診」
2017年 春号
「高齢者と運転」
「ワクチン接種について」
「震災6年目、忘れてはいけません」
2016年 冬号
「毎度おなじみ『禁煙のすすめ』です」
「新年に向けて」
2016年 秋号
「B型肝炎のワクチンが定期接種になります」
「今期の各種予防接種について」
2016年 夏号
「4月からの医療政策の変更点」
「校医・校医として感じること」
「最近気になること」
2016年 春号
「大人の発達障がい(神経発達症)」
「胃や腸の検査、X線とカメラ(内視鏡)のどちら?」
「 3月11日に想う」
2015年 冬号
「再びスマホ」
「医療保険のお話」
「医療の原点を考えさせてくれる映画」
2015年 秋号
「ワクチンに関するお知らせ」
「小児科の診察室から(待つことと急ぐこと)」
「帯状疱疹(ヘルペス)について」
「東北の被災地に行ってきました」
2015年 夏号
「5月31日は世界禁煙デーでした」
「スマホに子守をさせないで」
「 医療者としての願い」
2015年 春号
「子どもたちの未来のために」
「アレルギーのお話」
「発達障がいについて」
2014年 冬号
「今期の感染症情報」
「過活動膀胱」
「年末でも忘れてはいけないこと」
2014年 秋号
「今期のワクチン接種について」
「ワクチンよもやま話」
「中性脂肪が高いといわれたら」
2014年 夏号
「夏の感染症について」
「待合室をリフォームしました」
「エコスタイル実施中」
「小児科医の想い~最近の世相」
2014年 春号
「予防接種制度の変更」
「胃がん発生の二重奏」
「4月から医療費が改定されます」
「あの震災から丸3年経ちました」
2013年 冬号
「ウイルス?細菌?どう違う?」
「予防接種の接種回数」
「エコ生活の工夫と楽しみ」
「小学生の男の子の体験談」
2013年 秋号
「ワクチンについて」
「腰が曲がる前に・骨折を起こす前に」
「保育園や幼稚園に通う子どもたちの健康のために(第3版)」
「カフェレスト木馬とNPO法人・ゆうこうの家」
「福島の子ども達のその後」
2013年 夏号
「予防接種関連いろいろ」
「小児科医の想い」
2013年 春号
「ワクチンの定期接種」
「垣間見たアメリカの医療事情」
2012年 冬号
「人は血管と共に老いる」
「改めて禁煙の勧め」
2012年 秋号
「『ガン適齢期』」
2012年 夏号
「予防接種制度の見直しと今後の見通し」
「NPO法人『ゆうこうの家』と 喫茶『木馬』」
2012年 春号
「花粉症のお薬」
「新しいワクチン」
「認知とは?」
2011年 冬号
「予防接種で予防できる病気」
「予防に勝る治療なし(未病)」
「内部被爆と外部被爆」
2011年 秋号
「インフルエンザ予防接種の接種量が変わりました」
「震災後半年。今私たちにできること」
2011年 夏号
「ワクチンで予防できる病気」
「夏です。こんな病気に気をつけましょう」
「チャンピックス(禁煙補助剤)」
2011年 春号
「新ワクチンの認可、中止、そして?」
「心の病気」
2010年 冬号
「任意予防接種の全額助成」
「時間外の救急受診」
「慰安旅行記(台北)」2010年 秋号
「ワクチン行政の流れ」
「ワクチンに関する豆知識」
「名古屋市におけるワクチンの助成」2010年 夏号
「いろいろな夏かぜ」
「8月の思い」2010年 春号
「再々度新しいワクチンについて」
「当院でできる検査」2009年 冬号
「新型インフルエンザ 三たび」
「内科の診察で何がわかるの?」2009年 秋号
「今秋のワクチン情報」
「続・新型インフルエンザ」
「再び子宮頸がんについて」2009年 夏号
「夏のトラブルいろいろ」
「新型インフルエンザ」
「ワクチン情報」2009年 春号
「花粉症対策」
「インドネシア人留学生の投書」
「医療機関で配布される薬剤情報について」2008年 冬号
「ワクチン情報」
「冬の定番ウイルス」
「ベトナムのツーズー病院を訪ねて」2008年 秋号
「インフルエンザワクチン豆知識」
「新しい禁煙薬」「外来小児科学会」2008年 夏号
「溶連菌感染症が流行っています」
「"プラスことば"と"マイナスことば"」2008年 春号
「麻疹・風疹ニ種(MR)混合ワクチン3期・4期」2007年 冬号
「胃腸風邪が流行っています」
「地球のために・子供たちの未来のために」2007年 秋号
「予防接種の勧め」
「外来小児科学会」
「来年度からの新制度について」2007年 夏号
「汗をかこう」
「健康で楽しい老後を…骨粗しょう症を予防しましょう」他2007年 春号
「いまどきの医療事情」2006年 冬号
「風邪かと思ったら・・・」
「再び・禁煙の勧め」2006年 秋号
「外来小児科学会のご報告・感想」2006年 夏号
「オムツはいつとるの?」
「メタボリックシンドローム」2006年 春号
「点滴のお話」「血液検査のお話」2005年 冬号
「インフルエンザについて」
「予防接種のお話」
「胃のピロリ菌感染」2005年 秋号
「病気の予防に取り組みましょう」
「日本外来小児科学会年次集会の報告」2005年 夏号
「食中毒や熱中症、日焼けに注意!」
「新しいワクチン体制」2005年 春号
「風邪?それとも花粉症?」
「夜のトイレが近いのですが」2004年 冬号
「混合診療解禁って何?」
「STD(性感染症)とHIV(エイズ)」2004年 秋号
「我が家の子育てチェックリスト(外来小児科学会のご報告)」2004年 夏号
「夏の健康便り」2004年 春号
「(軽度)発達障害児・者に対する地域医療を目指して」2003年 冬号
「冬に流行する病気と留意点」2003年 秋号
「外来小児科学会のご報告」2003年 夏号
「夏の健康チェックポイント」2003年 春号
「ぐっすり眠れるためには」2002年 冬号
「インフルエンザQ&A 」2002年 秋号
「小児の救急 医者の本音・患者の本音」2002年 春号
「仮面うつ病という言葉を御存じですか」2001年 秋号
「骨粗鬆症について」
「歩き疲れを取る簡単マッサージ」
予防接種・検診のご案内
当院で行っている各種検診、カウンセリング、予防接種、禁煙指導などのご案内です。
→ご予約はこちらからどうぞ
受診されるときは・・・
待ち時間を極力減らし、スムーズに診察を行うために、ご協力をお願いいたします。
NPO法人 ゆうこうの家
当院の療育部門は「NPO法人 発達・心理相談センターゆうこうの家」として 独立しました。
夜間や休日には
名古屋市東部・南部で
夜間・休日に受診できる施設と
電話相談窓口のリストです。
受診の前に・・・
→子供の発熱時の看護
リンク
提携医療機関等のリンクです。
メール
八事の杜新聞 季節便り 2012 冬
初冬というのに異常な寒さです。異常な暑さの後なので、体がついていけません。
今朝(11月28日)のニュースで、登別市では猛吹雪の為全市停電で避難者もあるということです。
さて、ここのところ、A型インフルエンザ発生の情報がチラホラ入ってきますが、流行の山がいつごろか、どの程度かは今のところ予測不明です。インフルエンザワクチンはかかるのを防ぐことは出来ませんが、重症化を予防しますので、急いで済ませていただきたいと思います。
11月中旬からノロウイルス胃腸炎が多発し家族感染も多いです。軽い場合は気持ち悪く、少しだるいかなという程度ですが、重くなると何度も吐いて発熱と下痢を伴い、口の中もねばねばと乾いて、ぐったりします。こんなときは脱水症状ですので、点滴すると早く回復します。
ロタウイルス下痢症も症状は同じですが、ノロよりも重症感があります。
ロタウイルスワクチンが助成により半額で接種できますので、かかる子どもが減ることを願っています。
RSウイルス感染症、マイコプラズマ感染症、百日咳はいずれも風邪症状で始まります。
幼い子がRSウイルスに感染すると呼吸障害を起こしやすいので、息苦しそうで哺乳もままならないようなら、検査してもらいましょう。数分で結果が分かります。
学童期の長引く咳と熱はマイコプラズマ感染症を、成人の長引く咳は百日咳を第一に考えて治療しています。
 人は血管と共に老いる
人は血管と共に老いる
医学の世界では、昔から人は血管と共に老化するという常識があります。ということは耐用年数が過ぎた人(?!)でも血管が若ければまだまだ元気に過ごせるという事です。いうなれば、血管は人間の生命線であり、例えば、脳や心臓の血管が切れれば、命も切れるということもあり得ます。
血管を適切にメンテナンスするための五箇条
- 血圧を正常に保つこと(最高130-110/最低84以下 破裂出血や閉塞予防)
- 甘い物、脂肪分、塩分は控えめに、蛋白質は充分にとる
(菜食主義者には百寿に達する人は殆どいません。) - 糖尿病、腎臓病、過度の肥満は治療し、禁煙すること
- 適度な運動で筋力を鍛えること(血行をよくし、関節、骨を保護し、骨折を防ぐ)
- 常に好奇心を持ち、積極的に外に出て、趣味やおしゃべりなどの活動をし、脳の血のめぐりをよくすること(精神的な若さを保つ)
家縛りは「廃用萎縮症候群」につながります。
このような血管のメンテナンスを充分に意識して、健康・長寿をめざして下さい。
 改めて禁煙の勧め
改めて禁煙の勧め
当院は1988年の開業以来、院内禁煙としています。
開業当時は玄関先には一日でちりとり半分ほどの吸殻が捨てられていました。禁煙ムードの高まりから、最近は1日で数本です。
今年1月から9月までに小児科を受診された約200家族の喫煙状況を調べたところ、凡そ70家族が主に父親が喫煙していました。多くはベランダや、換気扇の下でとなっていますが、吐き出す煙にも有害物質が含まれていて、数十分吐き出されますので、受動喫煙は免れません。
タバコ一本が汚す空気の量は約ドラム缶500個分といわれます。
吸っていないとき、くすぶり続けるタバコから出る副流煙は不完全燃焼のため、主流煙(吸い込む煙)の何十倍もの有害物質(アンモニア、ニッケル、ホルムアルデヒド、カドミウム、ベンツピレン、ニコチン、一酸化炭素、ベンゼン、窒素酸化物など)を含んでいます。
小児科学会などは「タバコは子どもの第五の虐待」「子どもは歩く禁煙マーク」などのキャッチフレーズで、子どもを受動喫煙から守ろうとしています。吸わない人を受動喫煙から守ることは、吸う人の体も守るということです。
当院の禁煙外来は予約制ではありません。いつでも気軽にご相談下さい。
 最近気になること
最近気になること
当院にこられるアラブ系のお父さんの子、びっくりするほど長いまつげと、パッチリ目。つけまつげの人はさぞうらやましいことでしょう。
先日一歳半健診にこられたお母さん、長いつけまつげと濃い化粧で素顔はどんなかな。この子はお母さんの顔をどんな風に覚えるのかなと、ついいらぬ心配です。
清潔なきれいさには好感が持てますが、もともときれいな若い肌を化粧でカバーし、カラーコンタクトと、つけまつげをしているのを見ると、そのうち皮膚と目のトラブル(眼瞼下垂など)が出てきはしないかと気になる・・・
若い人には外見も心も、自分らしさに誇りと自信をもって欲しいと心から思います。
 異常な気候に突然の選挙!
異常な気候に突然の選挙!
忙しい年末に政情はばらばら、国民はあっけに取られて見守るのみ、そんな構図が見えます。
エネルギー政策、消費税、TPP,福祉と社会保障、憲法などたくさんの課題が山積しています。
名古屋大学で研修中のイラクの小児科医の話によると、イラクでは劣化ウラン弾による内部被爆で、出生児の1/3に重大な奇形が見られるということです。
Ⅹ線などの放射線を扱う機会がある私たちは、放射能のメリット・デメリット、またその本当の怖さを知っています。人間の制御範囲を超える原発はエネルギー源としてふさわしくありません。
また日本医師会はTPP参加によって、世界に誇る国民皆保険がなし崩しになる可能性があるとして反対しています。
原発と津波の被災者も、仕事を得られない若者も、希望を持てるような社会、上空を戦闘機が飛ばない安全な社会、何よりも命が大切にされる社会に向けて意志表示をしたいものです。



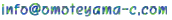
 2012年 秋号
2012年 秋号